1300年の歴史を歩く。国宝の宝庫・興福寺の魅力を徹底解説!
古都奈良のシンボルとして、静かに時を刻み続ける興福寺。
一歩足を踏み入れれば、そこは1300年以上の歴史が息づく荘厳な空間です!
日本で2番目に高い五重塔、憂いを帯びた表情で人々を魅了する阿修羅像、そして2018年に約300年ぶりに復興した中金堂など、見どころは尽きません…!
ここでは、藤原氏の氏寺として栄華を極めた興福寺の奥深い歴史から、必見の国宝仏、アクセス方法まで、その魅力を余すところなくご紹介します。
奈良公園の鹿たちに迎えられながら、日本の仏教美術と歴史の中心地を巡る旅に出かけましょう!
藤原氏と共に歩んだ、栄光と苦難の歴史
興福寺の歴史は、飛鳥時代まで遡ります。
藤原鎌足の妻・鏡女王が夫の病気平癒を願い、669年に京都の山科に建立した「山階寺(やましなでら)」がその前身です。
その後、飛鳥の厩坂(うまやさか)を経て、和銅3年(710年)の平城京遷都に伴い、鎌足の子である藤原不比等によって現在の地に移され、「興福寺」と名付けられました。
以来、興福寺は藤原氏の氏寺として、一族の隆盛と共に寺勢を拡大。
平安時代には広大な荘園と多くの僧兵を擁し、比叡山延暦寺と並び「南都北嶺(なんとほくれい)」と称されるほど絶大な権力を誇りました。
しかし、その道のりは平坦ではありませんでした。治承4年(1180年)、平重衡(たいらのしげひら)による「南都焼き討ち」によって、創建以来の伽藍のほとんどが焼失するという悲劇に見舞われます…。
その後、鎌倉時代に仏師・運慶らによって力強く復興を遂げますが、その後も度重なる火災に見舞われ、焼失と再建を繰り返してきました。
江戸時代の1717年の大火では、中金堂などが焼失し、財政難から長らく仮堂のままでしたが、平成30年(2018年)に創建当初の姿で再建されるなど、今もなおその歴史を紡ぎ続けています!
絶対に見逃せない!興福寺の必見スポット
広大な境内には、国宝や重要文化財に指定された貴重な建造物が点在しています!
ここでは、特に訪れておきたい見どころをご紹介します。
奈良の空にそびえる「五重塔」(国宝)

興福寺、そして古都奈良の象徴ともいえる五重塔!
高さ50.1メートルを誇り、京都・東寺の五重塔に次いで日本で2番目に高い木造塔です。
最初に建てられたのは天平2年(730年)、光明皇后の発願によるものでした!
その後、落雷などで5回も焼失しましたが、その度に再建され、現在の塔は応永33年(1426年)に再建された6代目にあたります。
幾多の困難を乗り越えてきたその姿は、まさに圧巻の一言です!
※現在、五重塔は明治以来約120年ぶりとなる大規模な保存修理工事のため、素屋根で覆われています。工事の完了は2031年(令和13年)の予定です。
300年の時を経て蘇った「中金堂」
興福寺の中心に位置する最も重要な建物が中金堂です!
藤原不比等によって創建され、7度の焼失と再建を繰り返しました。
享保2年(1717年)の火災後は、約300年もの間、仮堂のままでしたが、平成30年(2018年)に創建当時の壮麗な姿で復元されました。
堂内には、本尊である釈迦如来坐像を中心に、四天王立像(国宝)などが安置されており、その荘厳な空間に圧倒されます!
天平彫刻の傑作に出会う「国宝館」
興福寺を訪れたなら、国宝館は必見の場所です!
もともと僧侶が食事をする食堂(じきどう)があった場所に建てられ、興福寺が所蔵する数多くの国宝・重要文化財を収蔵・展示しています。
- 阿修羅像(国宝)
国宝館の至宝といえば、乾漆八部衆立像(かんしつはちぶしゅうりゅうぞう)の中でも特に有名な阿修羅像!
三つの顔と六本の腕を持つその姿と、憂いを帯びた繊細な表情は、見る者の心を惹きつけてやみません。
天平彫刻の最高傑作として、国内外で高い人気を誇ります。 - 千手観音菩薩立像(国宝)
旧食堂の本尊であった像で、その圧倒的な存在感に目を奪われます。 - 金剛力士立像(国宝)、天燈鬼・龍燈鬼立像(国宝)
鎌倉時代の仏師、運慶一門の作とされる力強い像。躍動感あふれる筋肉の表現が見事です。 - 仏頭(国宝)
もとは飛鳥の山田寺にあった薬師三尊像の本尊の頭部。
白鳳文化を代表する傑作です。
日本の国宝仏像の約15%を所蔵するともいわれる興福寺。
国宝館では、これら天平・鎌倉時代の至宝を間近で拝観できます!
優美な八角円堂「北円堂」と「南円堂」
境内には、特徴的な八角形の美しいお堂が二つあります。
- 北円堂(国宝)
日本に現存する八角円堂のうち、最も美しいと称えられるお堂です。
運慶の最高傑作との呼び声も高い、弥勒如来坐像(国宝)などが安置されています。普段は非公開ですが、春と秋に特別開扉されます。 - 南円堂(重要文化財)
西国三十三所観音霊場の第九番札所としても知られ、多くの参拝者で賑わいます。
朱塗りの鮮やかなお堂で、こちらも秋に特別開扉が行われます。
聖武天皇ゆかりの「東金堂」(国宝)
聖武天皇が叔母にあたる元正上皇の病気平癒を願って建立したお堂です!
堂内には本尊の薬師如来坐像(重要文化財)や、四天王立像(国宝)、十二神将立像(国宝)などが安置されています。
水面に映る五重塔が美しい「猿沢池」
興福寺の南に広がる猿沢池は、かつて興福寺の放生会(ほうじょうえ)が行われた池です!
水面に映る五重塔と柳の風景は、奈良を代表する景観の一つとして親しまれています。
御朱印めぐりも楽しもう
興福寺では、各お堂や国宝館にちなんだ様々な種類の御朱印をいただくことができます!
南円堂の納経所と、中金堂・東金堂の間にある勧進所で授与されています。
参拝の記念に、力強い筆致で書かれた御朱印を集めてみてはいかがでしょうか。
オリジナルの御朱印帳も用意されていますよ!
- 受付時間: 9:00~17:00
- 主な御朱印
- 中金堂「令興福力」
- 東金堂「薬師如来」
- 南円堂(西国三十三所第九番)
- 国宝館「千手観音」
- その他、各御詠歌など多数
拝観案内・アクセス
| 〒630-8213 奈良市登大路町48 | |
| 電車: 近鉄奈良駅から徒歩約5分 JR奈良駅から市内循環バスで約5分、「県庁前」バス停下車すぐ | |
| 境内: 自由 国宝館・東金堂: 9:00~17:00(受付は16:45まで) 中金堂: 9:00~17:00(受付は16:45まで) | |
| 国宝館: 大人 900円 東金堂: 大人 300円 中金堂: 大人 500円 ※セット券などもあります。詳細は公式サイトをご確認ください。 |
まとめ
1300年以上の長きにわたり、日本の歴史と文化の中心であり続けた興福寺。
度重なる災禍を乗り越え、今に伝わる貴重な建造物や仏像の数々は、私たちに深い感動と歴史の重みを教えてくれます。
特に、天平彫刻の傑作・阿修羅像との対面は、忘れられない体験となるでしょう。
奈良への旅行の際は、ぜひ興福寺に足を運び、その壮大な歴史と文化の息吹を肌で感じてみてくださいね!
- 興福寺について|歴史や概要を詳しく解説 – BesPes
- 興福寺の歴史ー略史1 – 法相宗大本山 興福寺
- 興福寺(奈良市) | 歴史文献で訪ねる奈良 | 奈良県歴史文化資源データベース「いかす・なら」
- 興福寺
- 22.興福寺 | 歴史街道
- 興福寺(奈良県/奈良公園周辺)のアクセス・営業時間・料金情報 – るるぶ
- 興福寺の仏像 – Wikipedia
- 中金堂 – 法相宗大本山 興福寺
- 中金堂(ちゅうこんどう) – 法相宗大本山 興福寺
- 五重塔 – 法相宗大本山 興福寺
- 祈り 未来へ ~興福寺五重塔 令和大修理~
- 【興福寺】歴史と見どころ5選+1 ~阿修羅像に会えるお寺! | ならこじ
- 興福寺 中金堂 | スポット一覧 – 【公式】奈良市観光コンシェルジュ
- 中金堂 アーカイブ – 法相宗大本山 興福寺
- 国宝館 – 法相宗大本山 興福寺
- 2019.02.12憂いのある美少年、阿修羅像に魅了される奈良・興福寺【山岡の仏像コラム】
- 阿修羅像【八部衆】(あしゅらぞう) – 法相宗大本山 興福寺
- 興福寺|スポット・体験|奈良市観光協会公式サイト
- 興福寺国宝館|奈良県観光公式サイト公式サイト公式サイト あをによし なら旅ネット|奈良市|奈良エリア|神社・仏閣
- 【国宝・世界遺産|興福寺】 拝観・見学のしかた 公式サイト補足情報
- 【阿修羅像・五重塔】「興福寺」見どころ&感想 – 散策ガイド – 平城ツーリズムドットコム
- 興福寺で御朱印10種類と御朱印帳を頂いたよ|時間など|奈良市
- 興福寺とは?多種類の御朱印が頂ける平城京の寺院に漲る1300年を超える歴史
- 御朱印・御朱印帳:興福寺(奈良県近鉄奈良駅) | ホトカミ – 神社お寺の投稿サイト
- 御朱印 – 法相宗大本山 興福寺
- 興福寺(南円堂・中金堂) 6種類の御朱印・御朱印帳紹介|頂ける場所、時間は?現地レポ(奈良)
- 【興福寺】アクセス・営業時間・料金情報 – じゃらんnet
- 興福寺中金堂 一般拝観|興福寺|奈良県観光公式サイト公式サイト公式サイト あをによし なら旅ネット|奈良市|奈良エリア|イベント・体験
- アクセス・駐車場案内 – 法相宗大本山 興福寺

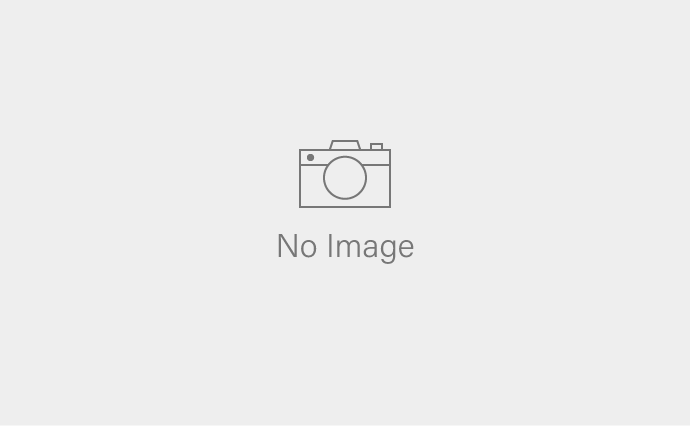
![興福寺国宝館|奈良県観光[公式サイト] あをによし なら旅ネット|奈良市|奈良エリア|神社・仏閣|神社・仏閣](http://yamatoji.nara-kankou.or.jp/contents/images/0000000096/IMAGE1.jpg)


